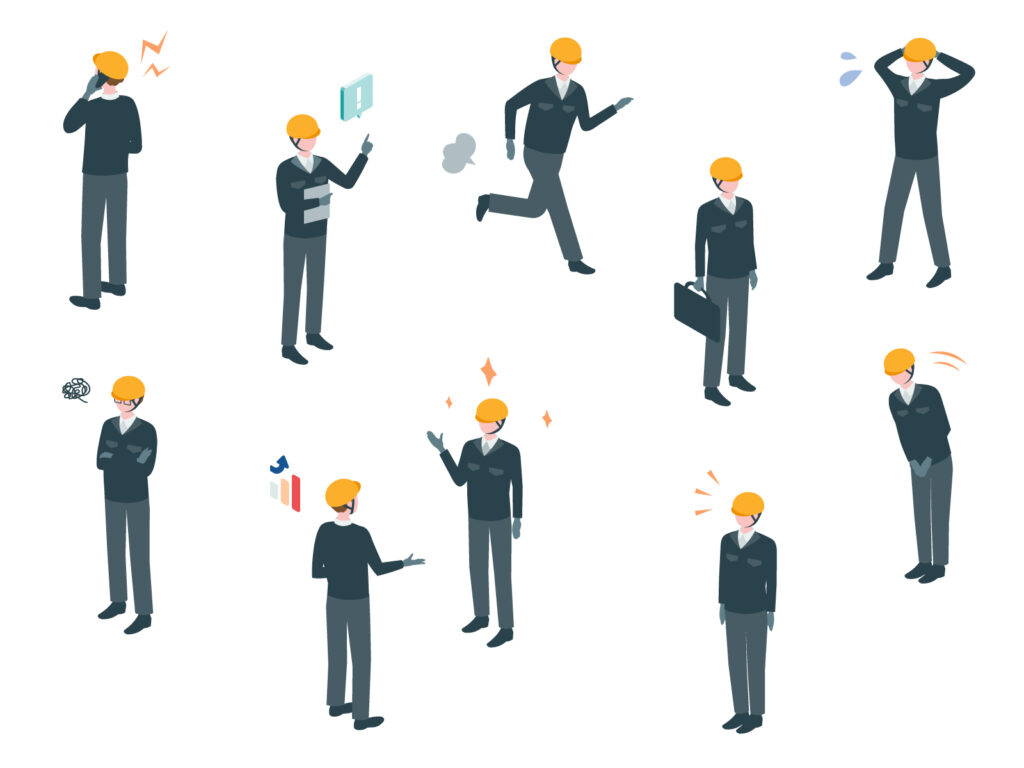1.土地家屋調査士
土地家屋調査士は、土地の分割、合併により土地の面積が変わった場合や、建物の新築、増改築が行われた場合に土地や建物の調査、測量を行い土地・建物の「表示に関する登記」の申請手続を代理する、不動産登記の専門家です。
「表示に関する登記」は、土地、建物の所有者に義務付けられていますが、この膨大に発生し、かつ義務である「表示に関する登記」を独占業務とすることが土地家屋調査士の強みといえます。
なお、登記の専門家というと、一般的には司法書士がイメージされますが、「表示に関する登記」は土地家屋調査士の独占業務となります。
2.難易度
★★★★☆
3.国家資格か民間資格か
国家資格
4.受験者数
毎年3,800人~4,500人
5.合格率
9.5~10%程度
6.業務の内容(独占業務の内容)
(1)不動産の表示の登記に必要な土地、家屋に関する調査及び測量
不動産の登記には「表示に関する登記(表題登記)」と「権利に関する登記」があります。
「表示に関する登記(表題登記)」とは、土地や建物の物理的状況を表示した登記で、土地については所在、地番、地目、地積、登記原因、所有者が、建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因、所有者が挙げられます。
この「表示に関する登記(表題登記)」は法律で義務付けられており、土地や建物を取得した者は原則として1ヵ月以内に申請しなければなりません。手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
一方「権利に関する登記」とは、不動産の権利(所有権、賃借権、抵当権など)の状況や変動を表示した登記で、その不動産の所有者は誰か、いつ取得したか、銀行の担保はついているか、などの情報が記載されており、さらに「所有権に関する事項(甲区)」と「所有権以外の権利に関する事項(乙区)」に分けられます。
土地家屋調査士の業務の1つとして、上記の「表示に関する登記(表示登記)」を行うために必要な土地や家屋に関する調査、測量が挙げられます。「表示に関する登記(表示登記)」は土地や建物を取得した者の義務で、土地の用途変更や分筆の際に、建物は新築や増改築、解体の際に必要となりますが、土地家屋調査士はこの継続的に発生し、かつ義務付けられている「表示に関する登記(表示登記)」のための調査及び測量を業務としているため、安定的に仕事が発生します。
(2)不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理
上記のとおり、不動産の表示に関する登記(表示登記)は所有者に申請義務が課されていますが、表示に関する登記(表示登記)を行うためには土地や建物の調査、測量が必要であり、一般の方が自ら行うことは現実的ではありません。そこで土地家屋調査士は所有者から依頼を受け、不動産の表示に関する登記(表示登記)の申請手続きを代理で行うのです。
なお、上記の「権利に関する登記」は司法書士の業務となり、こちらは義務ではなく、任意の登記となります。ただし、任意とはいえ「権利に関する登記」は第三者に対する対抗要件となりますので、ほとんどのケースで行われます。(ただし、相続等で権利を取得した際には、価値の低い不動産等では行われないケースも多い)
第三者に対する対抗要件とは、例えば売主Aと買主Bの間で成立した不動産売買の効力を第三者(AとB以外の人)に対して主張するための法律的な要件となります。この不動産売買を例に挙げると、不動産の売買が成立した場合に、「権利に関する登記」で所有者をA→Bに変更しておけば、この不動産の所有者はBですよということを第三者であるCやDやEに主張できますが、「権利に関する登記」で所有者をA→Bに変更していない状態で、何も知らないCが売主Aからその不動産を買受けた場合(AはBとCの2人に1つの不動産を売却したこととなる(二重売買))、Cが先に「権利に関する登記」を行うと、先に買い受けたBはその不動産が自分のものであるということを主張できなくなります(逆にCがその不動産の所有者であることを主張できる)。
(3)筆界特定の手続についての代理
まず土地の境界には、「筆界」と「所有権界」とがあります。
「筆界」とは、ある土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線をいいます。筆界は所有者同士の合意等によって変更することはできず、分筆や合筆の手続をとらない限り変動することはありません。一方で「所有権界」は所有権の範囲を示す線で、所有者間の合意で変更することができます。
「筆界」と「所有権界」は一致することもありますが、一致しないこともあります。
筆界特定制度とは、その土地が登記されたときの境界(筆界)について、現地における位置を公的機関が調査し、明らか にする制度です。この制度では、土地の所有者の申請に基づいて、筆界特定登記官(登記官は、法務局に勤務している公務員で、登記に関する事務を処理するための権限を有する者のことです)が民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定します。
土地家屋調査士はこの筆界特定の申請の代理を業務として行うことができるほか、筆界の専門家として上記の筆界調査員にも多数の者が任命されています。
7.活躍の場所
(1)土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士事務所は、大きく個人事務所と法人事務所に分けられます。
個人事務所は職員の人数が少なく、測量業務と登記業務で担当者を分けておらず1つの案件を最初から最後まで担当できるため、成長のスピードが早いという特徴があります。ただ一方で少人数で業務を回すため、繁忙期にはキャパシティーを超える業務を担当しないといけないこともあります。また案件の規模は法人事務所よりも小さくなりがちです。さらには給与や待遇、教育制度なども法人事務所に比べると見劣りするケースが多いようです。
一方法人事務所は土地家屋調査士が複数名所属していることが多く、規模の大きな事務所ですと、測量業務と登記業務で部門分が分かれているケースもあります。取り扱う案件の規模も個人事務所に比べると大きく、収入の安定や福利厚生の充実も期待できます。また教育や研修も行われており、成長の機会があると言えます。一方で分業であるため経験できる業務の幅は個人事務所に見劣りします。
(2) 測量会社
土地家屋調査士の試験合格後は測量会社に就職する方も多くいます。ただし、土地家屋調査士は公正な測量を行う必要があり、営利目的の企業に所属することができないため、測量会社に就職する場合には、測量会社に土地家屋調査士が所属するのではなく、別の併設されたグループ会社に所属することとなります。
また業務内容についても、測量会社にはすでに測量士が在籍しているため、測量業務ではなく、土地家屋調査士の独占業務である登記がメイン業務となることが考えられます。
測量会社は国や都道府県、市町村などの地方公共団体を顧客としているケースもあり、規模の大きな案件に携われる可能性もあり、やりがいをもって仕事に取り組むことができると考えられます。
8.独立の可否
土地家屋調査士も、独立開業も十分に目指せる資格です。
土地家屋調査士は前記のとおり土地、建物の所有者に義務付けられている「表示に関する登記」を独占業務とするため、独立後の仕事がなくなる可能性が極めて低く、廃業のリスクが少ない資格と言えます。
9.勉強時間
1,000~1,250時間
10.勉強方法
独学はほぼ不可能だと思います。試験範囲が広く、専門性が高く、さらに出題数の多い不動産登記法が試験科目に含まれるため、専門学校に通って勉強の範囲を絞って勉強するのが効率的です。
11.試験日
毎年10月第3日曜日